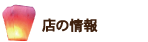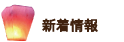炭鉱の文化
台湾では、オランダ統治時代にすでに石炭の採掘が行われていました。基隆地域で先ず採掘が始まり、平渓郷における採掘は日本統治時代 (明治40年/民国前5年(1907年))に開始されました。平渓庄の第一代村長、潘炳燭が地面に現れていた石炭を見つけ、採掘権を獲得しました。大正7年/民国7年(1918年)には、日本の藤田組と台陽鉱業公司の創設者、顔雲年が共同出資して採掘と会社経営を開始、「台北炭鉱株式会社」を設立しました(後に「台陽鉱業株式会社」と改名)。これにより平渓郷は石炭採掘の時代へと突入しました。大正10年/民国10年(1921年)、顔雲年が巨額の資本を投入し、石炭運輸用の平渓線の線路を敷設しました。その後石炭は大量に採掘され、線路を使って輸送されるようになりました。一時は採掘場から駅までの間にトロッコがずらりと並び、つり橋や鉄橋が渓谷を貫きました。これらはすべて石炭採掘・輸送の必要性から生まれた産物でしたが、こうして平渓線の線路は平渓郷から外の地域への交通を開いたのでした。
石炭産業の勃興により、平渓郷の人口は急増しました。集落の分布や生活形態も大きく変わり、現在の平渓村、石底村、菁桐坑、十分集落が新たに形成されました。最盛期には、郷内に約18の炭坑がありました。炭鉱で働く労働者は四千人余りにも上り、全郷で80%の人々が石炭産業によって生計を立てていました。民国58年(1969年)、国際石炭採掘量の増加と品質の差異より、海外からの輸入石炭との価格競争に勝てなくなり、住民はだんだんと生活の糧である石炭採掘の仕事を失っていきました。大都市の工業地帯に移っていく者が増え、平渓郷は農村の静けさを取り戻していきました。