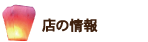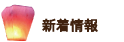発展の歴史
清の乾隆年間に、閩南人が福建省の泉州と安渓の二つの地からやって来て開墾し、山と基隆河に囲まれた場所で農業を営むようになりました。先住民の多くは薯榔や樟脳を採取したり、大青や茶葉などの作物を植えるなどして、素朴な生活を営んでいました。
西暦1907年、平渓庄の初代村長である潘炳燭が平渓の近くで地面に出ている石炭を見つけたことから、平渓郷の石炭産業の時代が始まりました。平渓は山中にありながらもあっという間ににぎやかな小都市に姿を変えました。その後、石炭運搬の必要性から、西暦1918年、台陽鉱業公司が出資して平渓鉄道の支線が建設されました。これにより平渓郷近辺において一世紀近く続く産業発展が始まり、現地の住民の生活形態と周辺の環境にも大きな影響を及ぼしました。
石炭産業の最盛期には、平渓支線では人々の声が沸きかえり、一儲けしようという夢追い人の数は数万人にも達しました。しかしながら、約十数年前から鉱山の生産量が減少、事故発生なども重なり、鉱山はあいついで閉鎖されました。平渓の栄華も徐々に色あせていきましたが、それに伴い農村は元の静かな村へともどっていきました。ただ、鉄道は炭鉱とともにさびれていくことはありませんでした。むしろ人々にとって鉄道は、石炭が平渓にもたらした栄光の日々と採掘工の艱難辛苦の生活という、往年の光と影を懐かしむよき拠り所となったのです。また、近年では外に出ていた平渓出身の若者たちが故郷に戻り、新しい村造りに参加するという動きがでています。天燈(ランタン)を上げる伝統にも希望の灯がともり、平渓郷は今、天燈の故郷として知られるようになりました。