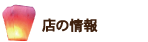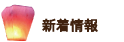製作方法
一般的にどんな物質でも熱せば膨らみ、冷やすと縮むという特性があります。熱の伝達方式から言えば、空気は熱せられると体積が大きく、密度は小さくなり、これにより上へと移動します。この時周囲の冷たい空気は流動し、底部の空間を埋めます。この繰り返しにより熱エネルギーが伝わり、熱の対流により天燈が上昇するのです。
- まず底の枠を作ります。長さ約220センチの竹ひご一本で丸い枠を作り、ゴムでかたく結びます。針金を真ん中で交錯させますが、燃料(灯油に浸した12枚の金紙)の取り付け用に少し針金を残しておきます。
- 長さ約4尺、幅3.6尺の画仙紙4枚を天燈の形に切ってから、机の上に広げ、重ねて置いておきます。縁を1.5センチ残して糊をつけ、左側から2枚目と3枚目を張り合わせ、次に1枚目と4枚目の左側を張り合わせます。
- 次に右側を張ります。まず1枚目と2枚目を張り合わせ、続いて3枚目と4枚目を張ります。
- 竹の枠組みと画仙紙の結合部分は、まず両面テープを竹の枠の外側に貼り、それから画宣紙の底の部分を貼り合わせます。
- 画仙紙を広げて竹枠を上から中に入れ、輪の四方を貼り付け、天燈のできあがりです。